「まずは型にはまってみよう」
高校の入学式の日に、母を通して言われた先生方の言葉。
なぜ「母を通して」なのかというと、新入生の帰宅後に行われた保護者だけの集まりで、そのような話がされたからなのだ。
気づかないまま、型にはまった大人になっていく
母は聞いてきたことをちゃんと教えてくれる。笑
私と同じく、よくメモをとる人である(似たのはきっと私のほうなのだが)。

「まずは型にはまってみよう」
当時、この言葉に対して特に抵抗はなかった。
高校入学以前から、自分にとって型にはまるのは当たり前のことだったから。
むしろ、そうしないほうがおかしいと思っていた。
(型にはまろうとしない友達に腹が立つこともあったし、なぜそうなるのかも全く理解できなかった)
だから、先生方の最初の「期待」には答えられていたと思う。
集団生活だから、というのもあるだろうけれど…生徒への愛情とか、社会に送り出さなければならない責任とか、いろいろ含めての「型にはまろう」ということだったのだろう。

型にはまるのは全然構わなかったのだが、それによって自分の力(肉体的な力とか才能とか)を抑えることも当たり前になっていったと思う。
決められたところから出てはいけない、みたいな。
もちろん、当時はここまで言語化できていない。
「何だか分からないけれどもどかしい感じ」
「全力を出せているような気がしない」
「もっと頑張りたいけれど、これ以上頑張れない」
何となくそんな気がするなあ…程度だった。
自覚はほとんどしていなくても、いつの間にか「型にはまることにエネルギーを使っている」のだ。
本当は誰も、そんなつもりはなかっただろうけれど。
そして、大人になっても「型にはまろうとして力を抑える」ことをやめられない。
自分がそんな状態であることにも気づかないから。
ブログで自分を型にはめていた話
なぜ急にこんなことを書き始めたのかというと、最近、私が自分自身を「型にはめている」と感じたことがあったからなのだ。
このブログのことで。笑
(書いていても、書いていなくても、いつも気づきをくれるこのブログ…)
「このカテゴリーで発信していこう」と、先に決めると書けなくなる!
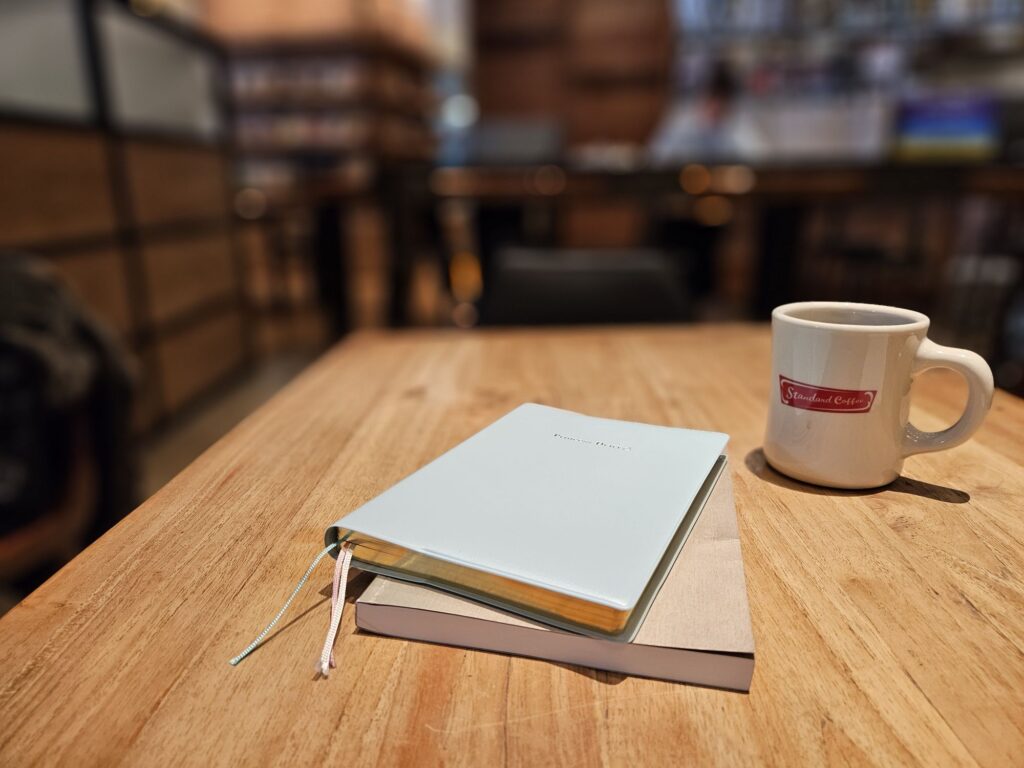
2〜3ヶ月前くらいに「6つくらいにカテゴリーを絞って書いていこう」と決めたのだが、それが見事に「縛り」となっていた。
どれだけネタが湧いて出ても、「これしか書いちゃいけません」って言っているようなものだから。
自分中でモヤモヤが大きくなり、このことについてノートでじっくり向き合った。
その結論…
記事を書いて公開することまでが喜びなのに、それができなくなってしまうなら、
「カテゴリー分けなんてあとで良くないか?」
だから、まずは書くことに集中して、記事を増やしながら分類していこうと決めた。
発信することが楽しいのだから。それをやらせてあげるのだ。

自分を縛るものは、意外と身近なところにある。気づいていないだけで。
好きなことや楽しいことを奪っているものはないか?
目にみえる人やものだけではなく、思い込みなども含めて。
自分の感じることに敏感になっていくのは、制限を取り払っていくためにも大切だなあ…と気づかされた話。



